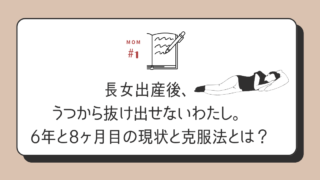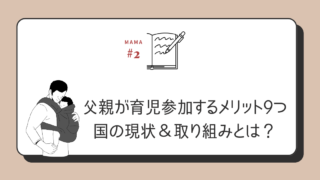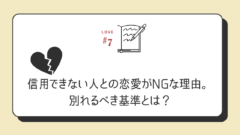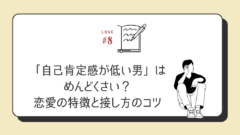「乳児死亡」「育児ノイローゼ」「ネグレクト」など、育児に関するネガティブなニュースが後をたたない世の中。
「かわいい赤ちゃんになんてひどいことを」「最低な母親」などと批判する人が多い中で、筆者はこのようなニュースを目にすると、そのお母さんの心情に思いを寄せずにはいられません。
また、「育児ノイローゼは甘えだ」と言う人も世の中には存在します。これも、苦しんでいる母親をさらに追い詰めてしまうことになるのではと懸念しています。
世間にも夫にも理解されないこのリアルな思い。これが、育児ノイローゼの現実です。
この記事では、筆者が経験したリアルな育児ノイローゼの症状とともに、今まさに育児に悩んでいる方たちが、治るまでの期間に少しでも笑顔を増やすための方法をお伝えします。
ぜひ、最後までチェックしてみてくださいね。
- 筆者が経験した育児ノイローゼの症状
- 育児ノイローゼになりうる理由
- 育児ノイローゼになりやすい人の特徴
- 育児ノイローゼが治るまでに気をつけたいこと

筆者であるわたしは、実はずっと「”産後うつ”かもしれない」という自覚がありました。しかし、育児ノイローゼの症状について調べてみると、どちらも当てはまることが判明。
さまざまな理由、さまざまな状況によって両方を併発していた筆者の経験が、「育児ノイローゼかもしれない」と悩む方の参考になれば幸いです。
筆者が経験したリアルな育児ノイローゼの症状7つ
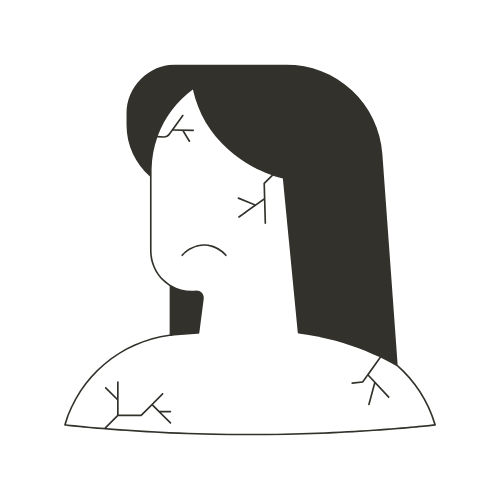
そもそも”育児ノイローゼ”と”産後うつ病”の違いについて、疑問をもつ人も多いので最初にお伝えしておきます。
育児ノイローゼ:
育児疲れのストレスで心身の不調をきたした状態
産後数週間〜数か月の育児期全般に発症
比較的軽度な場合が多い
ストレス源から離れると症状が改善する
イライラ、不安、食欲低下、気力の低下、罪悪感など
産後うつ病:
ホルモンバランスの乱れによる精神疾患
出産直後〜半年以内に発症
脳の機能的問題が関わる重篤な病気
専門的な治療が必要な場合がある
理由なく涙が出る、赤ちゃんを可愛く思えないなど
産後うつとは違い、治療も薬もいらない育児ノイローゼ。
しかし、ストレスが限界を超えた状態で起こるこの精神的な不調は、赤ちゃん・幼児・小学生など子どもの年齢に関係なく起こります。
また、育児ノイローゼは育児疲れやストレスが原因のため、母親だけでなく夫である男性や周囲の家族に症状が出ることも珍しくありません。
筆者の場合、育児ノイローゼの症状は、子どもが新生児の頃からすでに出始めていました。以下に詳しく解説します。
1. イライラ・怒りっぽくなる
”イライラ”は、筆者が最もつらさを感じた育児ノイローゼの症状。夫だけでなく、生まれたばかりの子どもに対しても感情的に当たってしまっていました。
- 「なんで手伝ってくれないの?」「私ばっかり!」という不満が募り、強い口調になる
- 協力してくれても「やり方が違う」とイライラしてしまう
- 夫の言葉に過敏に反応し、涙や怒りが止まらなくなる
- 子どもが少し泣いただけで「なんで泣き止まないの!?」と強い焦りや怒りを感じる
- 泣き声を聞くたびに胸がざわつき、イライラが止まらなくなる
- 泣きやまない赤ちゃんに「もうやめて」「静かにして」と言ってしまう
さらに、「また怒ってしまった」「母親失格だ」と自己嫌悪に陥ることでもイライラ。
怒ったあと後悔するのに、次の日も同じことを繰り返してしまいイライラが悪化するという悪循環の中にいました。
2. 過食症状
筆者はもともと、”過食”という形でストレスを発散してしまうタイプ。これが育児ノイローゼの症状としても強く出ていました。
- 眠いのに何か食べてからでないと寝たくない
- 空腹ではなく「イライラ」「不安」「寂しさ」で食べてしまう
- 食事をしたばかりでもすぐに甘いものやスナックを口にしてしまう
- 食べているときだけ「ホっとする」と感じる
食べたあとに、「何やってるんだろう」「また太る…」といった強い罪悪感や自己嫌悪を感じ、それがストレスとなって再び食べてしまう、まさに悪循環。
また、当時の筆者は気分が落ち込みがちで、外出すら億劫だったため、唯一の楽しみが食べることだったような気がします。
「寝かしつけたらあれを食べよう」「せめて食べることで気を紛らわせたい」と、食べ物で気分を保っている状態でした。
3. 頭痛・肩こりなどの自律神経症状
産後、少なくとも1年間は、常に頭痛や肩こりに悩まされていました。
- 常に頭が重い・締めつけられるように痛む
- 頭や首、こめかみのあたりがズキズキする
- 育児の合間や夜になると痛みが強まる
- 天候・疲労・寝不足で悪化することが多い
- こりから頭痛・めまい・吐き気が出ることも
- マッサージや服薬で一時的に和らいでてもすぐに戻る
始めは「頻回授乳で睡眠不足だし、抱っこで肩がこるのは仕方ないか」と思っていたのですが、実は育児ノイローゼによる自律神経の乱れが原因だったのです。
4. 体のだるさや慢性的な疲労感
筆者は産後数年間、「体調がいい!」と感じられる日がほとんどなく、体が重く感じる・ずっと疲れが抜けないといった育児ノイローゼの症状がありました。
- どれだけ寝ても寝た気がしない
- 朝から体が重く、起き上がるのもつらい
- 「一日が始まるのがしんどい」と感じる
- 常に風邪のようなだるさがある
- 外出すると疲れるため引きこもりがち
- 動くと余計に疲れてしまうため、横になりがち
- 立ち上がるたびに立ちくらみがする
この他、仰向けになっているときに天井や床が揺れているような感覚になったこともあり、育児疲れだけが原因とは思えない疲労感を感じていました。
また、イライラや悲しみが強いときには体もどっと重くなり、頑張りたいのに体が言うことを聞かない日も。
5. 無気力・虚無感
筆者が自分に驚いた育児ノイローゼの症状は、出産前までは大好きだった音楽や映画、外出などに一切興味を持てなくなったことです。
流行りの曲やアーティストを追うことがどうでもよくなり、同じ趣味をもつ夫が聴いている音楽を「うるさい」と感じたことも。
- 「何も楽しくない」「何をしても虚しい」と感じる
- つらいのに泣く気力がなくなり涙が出ない
- 笑顔を作るのがつらい
- 「誰のために頑張っているのか分からない」と思う
また、育児の合間に家事をこなしても達成感を感じられなくなったり、身だしなみへの関心がなくなっていました。
6. 夫や家族への攻撃的な言動
「一緒に”親”になったはずなのに」と、夫に理解や協力をしてもらえないことへの怒りも、筆者が苦しんだ育児ノイローゼの症状のひとつ。
本当は「助けてほしい」「分かってほしい」という気持ちでいるのに、それを素直に言えず夫のちょっとした言葉や行動にイライラが抑えられなくなっていました。
- 普段なら抑えられる感情が一気に爆発する
- 夫が帰宅してスマホを見ているだけで「子ども見ててよ!」と怒鳴る
- 「大丈夫?」と優しく声をかけられても「大丈夫じゃないよ!」と強く言い返す
- 怒鳴る代わりに口をきかなくなることも
- 「苦しみを分かってくれない」「何もしない人」と夫に敵意を抱く
怒鳴ったり泣いたりしても気持ちが落ち着かず、「自分が怖い」「わたしってこんなんじゃなかった」と感じたことも。
また、「なんであんなこと言ったんだろう」「本当は助けてほしかっただけなのに」と後悔し、涙が止まらなくなる夜もありました。
7. 強い不安・焦り
SNSや育児サイトを頻繁に見ては、他の赤ちゃんと比べて焦ることは、育児中の女性によくあることかもしれません。
筆者の場合は心が常に張りつめた状態になってしまい、比較するたびに「私のせいだ」「まだ全然だめだ」と感じるようになっていました。
- 夫や親のちょっとした言葉に「ダメな母親だと思われた」と落ち込む
- 寝ない赤ちゃんに「私のやり方が悪いんだ」と自分を責める
- 「早く寝かせなきゃ」「お風呂までに家事を終えなきゃ」と常に焦っている
- 赤ちゃんが寝ても「起きたらどうしよう」と考えてゆっくりできない
- 「もし泣いたら」「周りに迷惑をかけたら」と外出が怖くなる
- 頭の中が常に“やることリスト”でいっぱい
常に頭のどこかに「自分の育児は間違っているのでは」という不安があり、気持ちに余裕のない状態での育児。
「ちゃんとしなきゃ」というプレッシャーが強すぎて、心身が疲弊しきっていました。
筆者が産後すぐに育児ノイローゼになった原因
一般的に、育児ノイローゼの主な原因は、育児ストレス・睡眠不足・孤独・過労だと言われています。
休養や周囲のサポートなどによって回復しやすいものの、「もう疲れた」「誰か代わって」という思いを抱えながらの育児は”出口の見えないトンネル”と同じ。
さらに筆者の場合、産後数週間で育児ノイローゼになったことで、娘が生まれた喜びよりも「育児がつらい」という子育てのスタートでした。
ここでは、筆者がなぜ産後すぐに育児ノイローゼになってしまったのか、考えられる原因について詳しくお伝えします。

実は、”育児ノイローゼ”は正式な医学診断名ではなく、心身のバランスを崩している状態。産後うつ病ほど重症ではないものの、限界に近い“疲弊した心のSOS” です。
筆者にその症状が出てしまった原因を知ることが、予防や改善に役立つかもしれません。ぜひ参考にしてくださいね。
終わりのないタスク
産後、想定外の出来事や思い通りにいかないことによるフラストレーションに加えて、
このような”終わりのないタスク”に心を追い詰められていました。
また、「こんなに頑張ってるのに報われない」「誰にも感謝されない」「家計のために役立ってない」という虚無感が徐々に強まったことも原因です。
睡眠不足
産後しばらくは昼夜問わず2時間おきの授乳。夜中に寝てくれないときは抱っこで寝かしつけ――。
これにより、日々の睡眠が断片化し、疲労とストレスが蓄積。気づいたときには感情が不安定になっていました。
夜中に熱を出したり、痛みを和らげるために搾乳し、寝不足のまま翌朝母乳外来へ…と対応に追われたことも。寝不足による不調に加え、乳腺炎の発熱や痛みは大きなストレスでした。
変わらない夫
妊娠前と同じ生活スタイル・価値観・行動を続け、筆者の身体や状況の変化・負担を理解できていなかった夫。
「俺は仕事で疲れてるんだ」と言い訳して育児に関わらない男性は多いと知ってはいたものの、実際に自分の夫がそうだとわかったことによるショックも影響したかもしれません。
母親にとって育児は“24時間労働”であり、休む暇のない重労働ですが、そんな夫の理解の欠如が「私だけが頑張ってる」「誰もわかってくれない」と孤立感を生んでいました。
また、休む時間もなく動き回っているときの「手伝ってあげている」という上から目線に強い不公平感を感じていたことも、大きなストレスでした。
ワンオペ育児

多忙な夫ですが自営業のため家にいる時間が長く、産後のサポートにはある程度期待をしていました。
しかし現実には、夫は家事全般が苦手なため即戦力とはならず、むしろ育児に加えて”夫のお世話”が増えたような状態に。
慣れない育児をしながらすべての家事を一人で担う状況は、筆者にとってかなりの負担になっていました。
「すべて自分でやらなければ」「赤ちゃんはわたしがしっかり見なきゃ」という張り詰めた気持ちも、育児ノイローゼを悪化させた要因だったかと。
これは筆者にとって、物理的な限界だけではなく、「味方がいない」「一番身近な夫に共感してもらえない」という精神的な限界でもありました。
完璧主義な性格
育児は予測できないことの連続で、赤ちゃんの生活リズムや体調も毎日変わります。
完璧主義な筆者は、そんな状況を許すことができるはずもなく、産後一気に精神的な負担がのしかかりました。
SNSや育児書で理想の母親像を見て自分と比べ、「あの人はちゃんとやれているのに、私はできていない」と自分を追い込んでいた時期もありました。
また、完璧主義な性格上、自治体の育児支援サービスなどを頼ることに対して、「できない母親みたいで悔しい」「人に頼る自分が許せない」と感じていました。
自由の喪失
もともとマイペースで、人にペースを乱されるのが苦手だった筆者。赤ちゃん中心の生活になり、これまでの自由が大きく制限されたことは知らないうちに心の負担となっていました。
- 「ようやく休憩できる」と思ったタイミングで聞こえてくる泣き声
- スキマ時間に延々と片付けなければならない家事
- 赤ちゃんを連れて自由に外出できないストレス
このように、何かにつけて選択肢が制限されることや、常に「家族のために」を優先しなければならない状況が続いたことが、育児ノイローゼにつながってしまったのです。
ママ友不足
同じタイミングで出産した身近な友達が何人かはいたものの、近所に住んでいるわけではなかったため、会ったり頻繁に連絡を取ったりすることはありませんでした。
産後数か月間、日々の生活に追われて信頼できる友人との交流をしなかったことも、育児ノイローゼになった原因のひとつだと筆者は考えます。
境遇を理解してもらえる人と話す機会がなかったことで、「私だけが大変」「誰もわかってくれない」と感じて孤独感が強まったのだろうと。
すぐに会えるママ友がいれば、情報交換や小さな相談で「自分だけじゃない」と安心できたかもしれません。
実家が遠い
産後すぐ、特に新生児~数か月の間は、赤ちゃんから少し目を離すことに抵抗を感じてしまいがち。
- 「お腹が痛いからしばらくトイレに入りたい」
- 「配達員さんの対応をしなければならない」
- 「髪を乾かしたい」
この「ちょっとだけ見ててほしい」が叶わない状況の積み重ねは、筆者の孤独感やフラストレーションを増幅させていました。
もちろん、実家が遠くてもワンオペでも、立派に育児をしている方はいます。「母親としての自覚が足りない」と思う方がいて当然です。
しかし当時の筆者は、赤ちゃんや家事のサポートが得られないストレスと、そんな負のループから抜け出せないことに疲弊してしまい、情緒不安定になっていきました。
育児ノイローゼになりやすい人の特徴とは?
実は、育児ノイローゼになりやすい人には、
- 頑張り屋で責任感が強い
- 完璧を求めてしまう
- 助けを求められない
などといった共通点があります。これは、真面目で優しい性格の裏返しでもあります。
また、「いくつかの特徴が重なると育児ストレスが心の限界を超えやすくなる」と考えられています。

筆者は、すべての項目に当てはまると言ってもいいほど、”育児ノイローゼになりやすい人”の典型でした。
予防のためにも、自分の性格やタイプは子育て開始前に知っておくべきポイントのひとつだと言えます。
ぜひチェックしておいてくださいね。
完璧主義で自分に厳しい
「育児はこうあるべき」「ちゃんとしなきゃ」と理想を高く持つタイプです。
その理想と現実のギャップに苦しみ、少しでも失敗すると「母親失格かも」と自分を責めてしまいがち。
赤ちゃんは思い通りにならない存在なので、完璧を求めるほどストレスが蓄積しやすいです。
また、周囲に頼ることに罪悪感を感じやすいところもあります。
1人で抱え込みやすい
「育児も家事も完璧にこなしたい」と頑張ってしまうタイプ。
責任感が強く優しい人ほど限界を超えても我慢してしまい、心身がすり減ってしまいます。
また、「自分が頑張らなきゃ」「夫も仕事で大変だから」と助けを求めない傾向に。
孤独な育児が続くと、ちょっとした泣き声にも過敏になり、心が追いつめられやすくなります。
頼れる人が少ない
実家に頼ることができなかったりママ友がいなかったりして、”話を聞いてくれる人”がいないと、孤独感が強まります。
他の家庭との比較ができず、「自分だけが上手くできていない」と感じることも。
これは、「人付き合いやコミュニケーションが苦手」なタイプと、「頼りたいけど頼る人がいない」の両方に該当します。
人とつながることは心のバランスを保つ大きな支えになりますが、孤立はノイローゼのリスクを高めます。
感情を抑え込みやすい
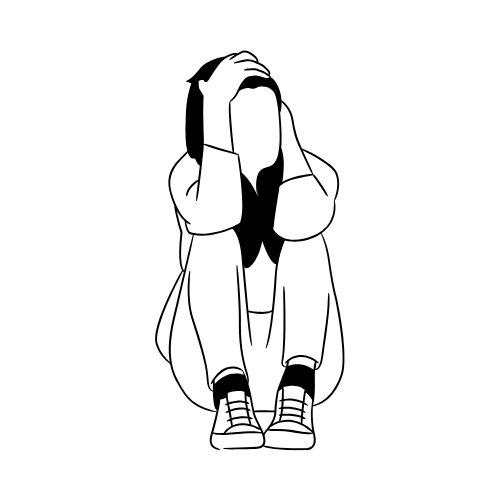
怒り・不安・悲しみをうまく表に出せず、”我慢”や”忍耐”で乗り切ろうとするタイプ。
表面上は穏やかでも、心の中では不満や孤独が積もっていき、ある日突然「何もしたくない」「泣きたくなる」といった形で爆発します。
もともと自分のことを「我慢強いから大丈夫」と思い込んでいる人でも、育児が始まるとこれまで通りにいかないことが多くなります。
また、感情のガス抜きが苦手な人ほど、精神的な疲労が深くなりやすいです。
環境の変化に弱い
産後は、生活リズム・睡眠・食事・社会との関わりなど、あらゆる環境が一変します。
変化に敏感な人ほど適応するのが難しく、自分のペースが乱れることに強いストレスを感じやすいです。
特に、出産前まで規則正しく働いていた人ほど、育児中心の生活への切り替えに時間がかかる傾向に。
また、感受性が強い人ほど、新しい環境の刺激によって脳が疲れやすく、心がすぐにいっぱいになります。
自由や自己表現を大切にする
「子育ては”自分の時間”や”思い通りに動ける自由”を奪う」と感じるタイプも、育児ノイローゼの症状が出る傾向に。
出産前に仕事・趣味・交友関係が充実していた人ほど、育児中心の生活とのギャップが大きく、ストレスを感じやすくなります。
また、これまで”女性らしさ”に気をつかっていたり、見た目にお金をかけていた人も、現実を受け入れにくいです。
「母親になっても自分らしくいたい」という気持ちを押し殺すことで、心が疲れてしまうのです。
他人の目や評価を気にしやすい
「ちゃんとしたママだと思われたい」「周りに迷惑をかけたくない」という意識が強い人は、つい自分を追い込んでしまいがち。
SNSやママ友との比較で劣等感を抱くことも多く、「自分はダメだ」と自己否定に陥りやすい傾向があります。
これは、生まれ持った性格や育った環境に起因するケースが多く、自覚の有無に関係なく育児中の女性を苦しめます。
他人の基準で頑張り続けることが、心の限界を超える原因になってしまうのです。
育児ノイローゼが治るまでの注意点
育児ノイローゼの回復には時間がかかることもありますが、少しでも笑顔を取り戻すためにできることは、毎日の中に小さくとも確実に存在します。
ここでは、「治るまでの期間に気をつけるべきこと」を整理してお伝えします。

筆者がまず試したのは、日々のこだわりを一旦捨てること。
例えば、お世話時間のルーティン。「〇時にお風呂に入れなきゃ」「2時間おきに授乳しなきゃ」という固定概念は、予定通りにいかないときストレスになるだけです。
また、「離乳食はぜんぶオーガニック食材で」「スキマ時間をすべて家事にあてる」などもやめました。
”自分流”を貫くのは素敵なことだけど、それがいつしか負担になることもあります。また、”自分流”にはムダや思い込みも多いもの。
まずは「思い切ってやめる」「不要な重荷を下ろす」ことから始めてみてくださいね。
「ちゃんとしなきゃ」を一度手放す
完璧なママを目指すほど、自分を苦しめてしまいます。家事ができなくても、離乳食が手作りじゃなくても大丈夫です。
子どもが笑っていれば、あなたの育児はすでに“十分”。「今日は生き延びた」「よく頑張った」と、自分に合格点を出してあげましょう。
無理に前向きになろうとしない
ポジティブでいなきゃ、笑顔でいなきゃ…と無理をすると、逆に心が疲れます。泣きたいときは泣いてOKです。
涙は心のデトックス。泣いた後に「少しスッキリした」と感じられるなら、それも立派な回復のサインです。
「ひとりの時間」を数分でも確保する
ほんの5分でもいいので、赤ちゃんと離れて「自分の呼吸に戻る時間」を作りましょう。泣かせっぱなしでも大丈夫。
トイレで深呼吸する、ベランダで空を見上げる、コーヒーを一口ゆっくり飲む――。その小さな“自分時間”が、心の回復力を育ててくれます。
周囲に「助けて」と伝える勇気を持つ
ママ友や家族・地域の支援センター・シッター・保健師などに頼ることは、弱さではありません。むしろ、“母親として強く生きるための正しい行動”です。
「お願いできることはお願いする」に対する抵抗心をなくすことで、心の余裕が少しずつ戻ってきます。
SNSの”理想のママ像”から離れる
キラキラした投稿を見るたびに、自分を責めていませんか?他人の”一瞬”を自分の現実と比べることには何の意味もありません。
子どもが求めているのは、目の前の”ママ”。スマホを置いて、わが子と目を合わせる時間を少し増やすだけでも、穏やかさが戻ってきます。
「今は回復の途中」と受け入れる
心の回復には波があります。良い日もあれば、また落ち込む日もある。それは“治っていない”のではなく、“治っていく途中”です。
焦らず、「今日は昨日より少しマシならOK」と、ゆるやかに歩いていきましょう。
まとめ
症状に当てはまるところがあっても、「私って育児ノイローゼなんだ…」と落ち込む必要はありません。
なぜなら、育児ノイローゼは、決して”甘え”でも”弱さ”でもないから。あなたの苦しみは、子どもへの愛情と、あなたの優しさの裏返しなのです。
毎日をどうにか乗り越えていること自体が、すでに強さの証です。
笑顔を取り戻すコツは、”頑張ること”ではなく、”力を抜く勇気を持つこと”。
また、「赤ちゃんが笑った」「温かいお茶が飲めた」といったほんの些細なことに気を留めるだけでも、脳は幸せを感じ取る力を取り戻します。

最後に筆者がお伝えしたいのは、「夫に期待しすぎてはいけない」ということ。
産後は、「わかってくれるはず」「どうせ分かってもらえない」と両極端に走りやすい時期です。期待しすぎても、無関心を装ってもストレスは溜まります。
夫のサポートが必要なら、“今の自分ができる範囲”と”サポートが必要な範囲”を具体的に伝えることで、家庭内のすれ違いを防ぐことができます。
笑顔は「作るもの」ではなく、「戻ってくるもの」。張り詰めた心をゆるめて、焦らず、少しずつ“心の体力”を取り戻すことが本当の回復へ近道ですよ。
あとから読み返したいときに活用してくださいね。