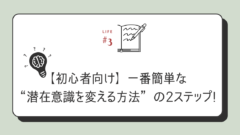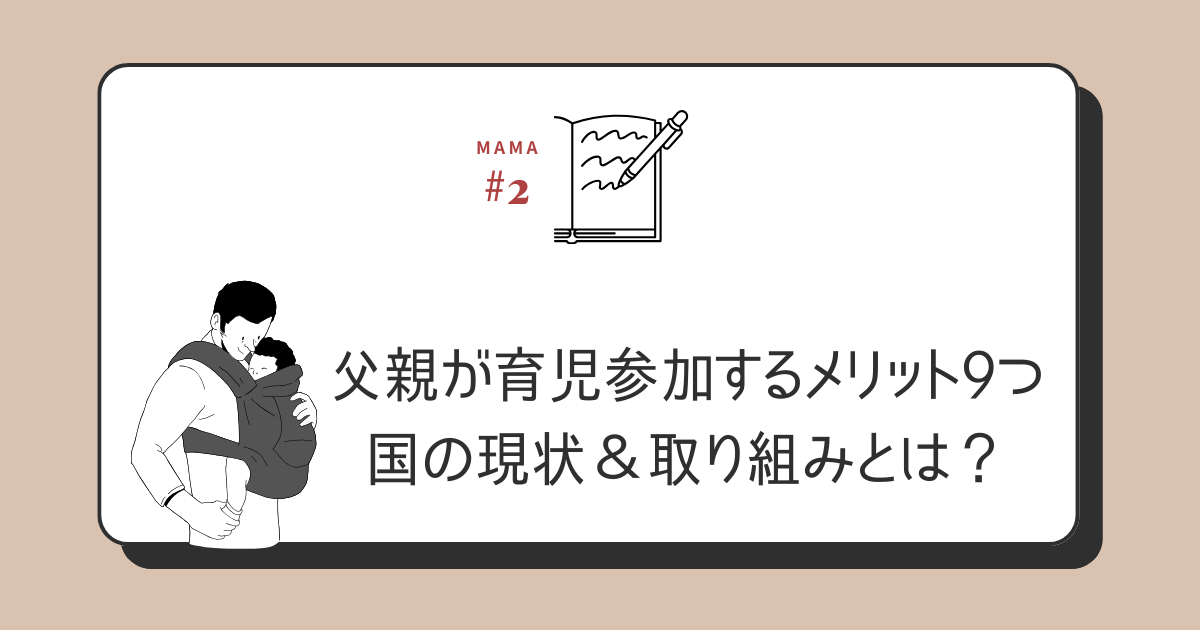
父親となったはずの夫に対して、「全然育児に参加してくれない」と感じたことはありませんか?
一緒にいるのに”ワンオペ育児状態”になってしまっている家庭では、妻が旦那にイライラしてしまい、子育てに悩んだり離婚を考えたりする確率が高まると言われています。
これは、SNSやさまざまなメディアで「イクメン」「子育てするパパは素敵」といったワードをよく目にするようになり、「男性は料理や家事をサポートして当然」という風潮が主流となった現代の縮図と言えるかもしれません。
近年では、厚生労働省が父親の育児参加を推奨するなど、国としても新しい動きを見せつつあります。
しかし、男性の育児参加に対する意識や実際のスキルが追い付いていないのが、今の日本の現状です。
この記事では、父親が育児に参加することのメリットについて掘り下げ、男性が育児に積極的に関わることが子どもや自身に与えるポジティブな影響を紹介します。
- 夫の育児参加について多くの女性が感じていること
- 父親が育児に参加することのメリット
- 男性の育児参加の現状と国の取り組み
- 夫に伝えたい”育児参加のポイント”

夫の育児参加は、筆者にとっても見過ごせない大きな悩みのひとつ。なんとか夫を変えようと苦しんだ時期もありました。
「育児は決して母親だけの仕事ではない」と理解していないのか、産後も行動や生活パターンを変えようとしない夫が無責任に見えてしまうんですよね。
ただし、育児参加を望む上で、夫の仕事状況や性格に合わせた最低限の配慮はすべきだと言えます。
この記事では共働き家庭やワンオペ家庭でも取り入れやすい男性の育児参加の方法もお伝えしますので、夫の育児参加について悩んでいる方は参考にしてくださいね。
”男性の育児参加”に関する妻の本音
自分から積極的に育児に参加しようとする男性もいますが、そうでない男性の方が多いのが現実。
育児参加しようとしない夫に対して女性は強いストレスを感じ、これが夫婦関係破綻のきっかけになることもあります。
また、”男性の育児参加”は一見すると家庭円満の鍵のように見えますが、実際には多くの妻たちが「手伝ってくれてるのになぜかストレスを感じる」という複雑な本音を抱えるケースもあるんです。
これは、女性特有の感情。
女性は男性よりも”共感”を求める傾向があるため、「夫にもっとやってほしい」よりも「夫にも同じように感じてほしい」と思う気持ちの方が強いのです。
まずは、このように多くの女性たちが夫の育児参加に感じている“本音”を詳しく見てみましょう。
「手伝う」ではなく「一緒に育ててほしい」
多くの妻が感じているのは、「夫が“手伝う”というスタンスなのが辛い」ということ。
育児は本来“母親の仕事を手伝う”のではなく、“二人の子どもを一緒に育てる”もの。
しかし夫が「何をすればいい?」と受け身だったり、頼まれた時だけ動く場合、妻は「私が常に指示を出さないといけない」という負担を感じます。
その結果、「だったら自分でやった方が早い」と、孤独を深めてしまうのです。
「やってくれるけど、気持ちがこもっていない」
夫がオムツ替えや寝かしつけをしてくれても、「なんか“義務的”で、心が感じられない」と感じる女性もいます。
これは、女性が“行動”だけでなく、“気持ち”をとても敏感に感じ取る生き物だから。
さらに、「俺も大変なんだよ」「やってあげてる感」が漂うと、妻は「理解されていない」「共感されていない」と心を閉ざしてしまうのです。
中には、無言でおむつ替えをする夫の姿に「もっと笑顔で話しかけながらすればいいのに…」と不満を感じる人も。
「育児の大変さをわかっていない」
夫の「家にいるのに全然家事が進まないね」「昼間、何してたの?」といった無意識な発言に、妻は深く傷つきます。
赤ちゃんのお世話は、時間の流れが普通ではありません。
1時間おきの授乳、泣きやまない夜泣き、食事やトイレ中も関係なく呼ばれます。
また、物理的な大変さに加えて、母親は「子どもの命を守らなきゃいけない」という無意識の責任も背負っているため、赤ちゃんが寝ていても「呼吸してるかな?」などと不安になることも。
「起きるまでにあれもこれも片付けなきゃ」「泣くかもしれないから今はできない」といった考えも頭を巡り、常に手いっぱいで気が休まる暇はありません。
そんな中で、「時間はあるのに、何も進まない」という感覚を夫に理解してもらえないと、妻は「私ばかり責められている」と悔しさやイライラを感じやすくなります。
「育児の“正解”を押しつけられたくない」
夫が「こうした方がいいんじゃない?」とアドバイスするつもりで言っても、妻にとっては「責められた」ように聞こえることがあります。
例えば、授乳のタイミングや寝かしつけのし方など、毎日の中で「これだ!」を見つけるために試行錯誤して頑張っている中で、普段何もしない夫のアドバイスはストレスにしかなりません。
特に、母親は常に「ちゃんとしなきゃ」というプレッシャーを抱えているので、小さな一言でも「ダメ出し」に聞こえてしまうのです。
その結果、「もう相談したくない」「一人で抱えよう」と心を閉ざしてしまうケースも多いです。
「頑張っていることを認めてほしい」
多くの妻が夫に最も求めているのは、”感謝”や”労いの言葉”です。
これには、「育児参加した夫に大変さを理解してもらい、自分の努力を知ってほしい」という思いが根本にあります。
女性は、「いつもありがとう」「本当に頑張ってるね」「ママのおかげで今日も気持ちよさそうに寝てるね」などの一言があるだけで、心がふっと軽くなるもの。
夫に自分と同じレベルを求めているのではなく、育児の大変さや辛い気持ちを分かち合いたいのです。
多くの女性が、「毎日大変だね」と共感されるだけで、“孤独な戦い”が“チーム育児”に変わることを望んでいるのです。
父親の育児参加がもたらすメリット9つ
父親の育児参加は、母親を助けるだけではなく、家族全体の幸福度を底上げする重要な要素。
実際、心理学・発達学の研究でも、父親が積極的に育児に関わることは、子どもの発達・母親のメンタル・夫婦関係のすべてに良い影響をもたらすことが分かっています。

さまざまな研究結果として男性の育児参加のメリットが証明されていることは、とても興味深いですよね。
筆者は何年か前に「パパに絵本を読んでもらうと子どもの想像力や語彙力に良い効果がある」ということを知り、時々読んでもらうようにしています。
このように、父親が育児参加することのメリットを詳しく見ていきましょう。
① 子どもの発達へのメリット
自己肯定感が高まる
これは心理学や発達研究でも多く報告されていることで、父親が日常的に関わることで子どもの「自分は愛されている」「自分には価値がある」という感覚が強く育つことがわかっています。
抱っこしたり、一緒に遊んだり、話を聞いたりと、父親が関わることで、子どもは「自分は大切にされている」というより強い実感を得ます。
特に、遊びの中でのスキンシップや冒険的な体験など、母親とは違う関わり方が効果的。
また、男の子にとっては父親が”同性のモデル”、女の子にとっては”異性の原型”となります。
父親から褒められたり認められたりする経験は、「社会に出ても自分は大丈夫だ」という自信を支える基盤になるのです。
普段はどうしても母親と接する時間の方が長くなりがちですが、父親との直接的なコミュニケーションを通して愛情を感じることで、心の安定や自信につながり、自己肯定感の高い子どもに育ちやすくなります。
社会性やコミュニケーション力が育つ
父親は、母親とは違う刺激を子どもに与えることができます。
例えば、母親よりも体を使ったダイナミックな遊びや、ちょっとした競争・挑戦を遊びの中に取り入れることが多い傾向に。
すると子どもは、取っ組み合い遊びやボール遊びの中で「やりすぎると相手が痛い」「負けてもまた挑戦できる」といった感覚を自然に身につけていきます。
こうした遊びを通して、子どもは「ルールを守る」「順番を待つ」「加減を覚える」といった社会的スキルを体験的に学ぶことができるのです。
父親は、母親よりも“説明的”で論理的な言葉を使うことが多く、これは子どもにとって「考えて話す訓練」に。
「なんでそう思ったの?」「どうしたらうまくいくかな?」といった問いかけが、子どもの思考力や表現力を刺激します。
また、父親が感情を言葉で伝える姿を見て育つと、他人との関係づくりが上手い子になりやすい傾向があることもわかっています。
学力・集中力にも良い影響
父親は母親よりも、子どもに”少し難しいこと”や”新しい挑戦”を促す傾向があります。
例えば、「自分でやってみよう」「最後までやり切れるかな?」といった声かけをすることで、子どもの“困難に向き合う力”を育むのです。
この経験は、学習場面でも”すぐに諦めない集中力”や”挑戦を楽しむ意欲”につながることも。
また、父親の「なぜ?」「どうして?」と考えさせるような質問が“考える力”を鍛えます。こうした対話は、言葉の理解力や文章読解力を育てるうえで非常に効果的。
実際に、父親がよく話しかけたり本を一緒に読んだりする家庭の子どもは、語彙力や国語の成績が高い傾向があることが報告されています。
父親の関わる遊びは、身体的・空間的な感覚を使うものが多く、脳の前頭前野(集中・判断・計画を司る部分)を刺激します。
特に、ブロック遊びやボール遊び、パズルなどは、手先の動きや空間認識力を鍛えるうえで非常に効果的。これらの遊びを通じて、「集中して考える力」「先を予測する力」が自然と身につきます。
② 母親へのメリット

わたしのように、「夫が育児にもっと参加してくれてたら、こんなに精神的に追い詰められることはなかった」と感じている女性も多いはずです。
これは単に「手伝ってくれるから楽になる」という表面的なことではなくて、母親の“心の安心”や“自分らしさの回復”に直結するもの。
男性の育児参加が母親にもたらすメリットを詳しく見ていきましょう。
精神的な負担が軽くなる
産後の母親が最もつらく感じるのは、実は“身体の疲れ”よりも“孤独”なんですよね。
一日中子どもと二人きりで過ごしていると、泣き声に対応し続ける中で、「誰にも理解されない」「自分だけが頑張っている」と感じやすくなります。
しかし、父親が育児に関わることで、母親は「一緒に子どもを育てている」という安心感を得ます。
たとえ家事や育児の分担が完全に半々でなくても、“共に向き合っている”という気持ちの共有が、孤独感を大きく軽減するのです。
また、父親が子どものお風呂や寝かしつけ、送り迎えなどの一部を担うことで、母親に“ひとりの時間”ができます。
このわずかな時間でも、コーヒーを飲んだりスマホを見たり、外に出たりするだけで気持ちはリセットされます。
結果として、子どもに対しても穏やかに接することができ、イライラや罪悪感の連鎖を断ち切る効果があります。
夫への信頼感と愛情が深まる
厚生労働省や大学の共同研究による調査では、夫が育児・家事に積極的に参加する家庭ほど、妻の満足度と夫婦関係の安定度が高いことがわかっています。
例えば、多くの母親が”夫が子どもをあやしている姿”を見たり、”子どもに優しく語りかける声”を聴いて、改めて「いい人だな」「この人と結婚してよかった」と感じます。
恋人時代には見られなかった“父性”や“責任感”が、女性にとって新たな魅力として映るのです。
また、産後の母親は、体調の変化・ホルモンバランス・睡眠不足によって、心身ともに不安定になりやすい時期。
そのときに夫が無関心だったり、言葉足らずだと、「自分は一人で頑張っている」という寂しさにより愛情が冷めていくことがあります。
一方で、夫が「今日大変だった?」「俺がやっておくよ」と寄り添うだけで、母親の中に「この人は私の気持ちをわかってくれる」「ちゃんと見てくれている」という感情が芽生えます。
つまり、父親の育児参加は「夫婦仲を良くする最強の行動」とも言えるのです。
「産後うつ」の予防・回復につながる
父親が育児に積極的に関わる家庭ほど、母親の産後うつの発症率が低いことが多くの研究で報告されています。
これは、母親が心身の休息と心理的サポートの両方が得られることで、ホルモンバランスの変化やストレスに対処しやすくなるためです。
また、「これ毎日やるの大変だね」という夫の共感や、「一緒にやっている」という感覚は心理的に産後うつの大きな防御に。
「自分一人で抱え込んでいる」という孤独感が和らぐと、自己否定・絶望感のようなうつ的思考が弱まりやすくなります。
つまり、父親の育児参加は母親のメンタルヘルスの安定を支える“最前線”でもあるのです。
特に、以下は短期で効果が出やすいです。
夜間シフトを分担する: 「週2回は父が夜対応」など。母の睡眠確保&ストレス軽減に直結します。 母が休めるまとまった時間を定期的に作る: 2〜4時間、夫と子どもだけで昼間に外出してもらう。パパ友がいると受け入れやすいケースも。 “父が主担当になる仕事”を決める: お風呂、外遊び、寝かしつけなど。父の“成功体験”を作ることが継続的な育児参加に繋がります。
③ 父親自身へのメリット

多くの男性にとって、育児は「負担」「しんどい」といったネガティブなイメージが根強くあります。
でも、育児が父親にもたらすのは、デメリットよりも圧倒的にメリットの方が多いんです。ぜひパパに知ってもらいたいポイントをお伝えします。
子どもとの絆が深まる
子どもとの信頼関係の形成は、まだ意思の疎通が取れない赤ちゃんの頃から始まっています。
父親が小さな子どもの動きや表情の変化に対して敏感に応答し続けると、子どもは「この人は自分をわかってくれる」「助けてくれる存在」だと学ぶのです。
また、抱っこや肌の触れ合い・スキンシップは、生理的・情動的な結びつきに重要な”オキシトシン”の分泌を促し、父子双方の安心感と親しみを高めることがわかっています。
そして何より、子どもが笑顔を見せたり喜んだりする姿を見ることで、父親は「自分も育児で役に立てる」と実感します。
これがさらに育児への関わりを増やし、絆を強める好循環を生むことに。
「父親としての自信」や「家族の一員としての実感」を得られることは、仕事へのモチベーションにも良い影響を与えてくれますよ。
ストレス軽減・幸福感の向上
意外ですが、子どもとの触れ合いは父親のストレスを軽減する効果もあります。
大規模な研究でも、脳科学的にスキンシップや笑いが幸福度を高めるとされています。
低所得やストレスの高い環境でも、父親の関与が高いほど父親自身の抑うつリスクが低いという結果が報告されているんです。
一方で、父親にも産後期に抑うつや不安を経験する人が約1割程度存在し、負担が過度になると逆にストレスになる可能性があります。
どんな男性にも育児参加が向いているわけではなく、”質”と”サポート”が重要だとする研究も。
男性が育児に参加する上で大切なポイントは、抱っこやお風呂などの日常的なスキンシップや、一貫した得意分野の担当・遊びといった実行しやすい行動を続けること。
父も家族も確実にプラスを感じられます。
④ 家族全体のメリット
家庭が明るく、安心できる空間になる
父親が育児に関わる家庭は、母親も子どももリラックスできる“安全基地”になりやすいです。
また、家族内でのコミュニケーションが増えると家庭内に笑顔が増えるため、家族全員のメンタルが安定します。
最も理想的なのは、夫婦で分担・連携がとれること。責め合いやけんかが減り、問題が起きても「二人で解決しよう」という姿勢になりやすいです。
家族それぞれへの具体的なメリットをお伝えします。
子ども:
感情表現がしやすくなり、自信や社会性が育つ
親に素直に頼ったり甘えたりできるようになる
母親:
孤独感・疲労が和らぎ、メンタルが安定しやすい
些細なミスで夫を責めなくなる
疲労感・イライラが減り、表情や言動に余裕が出る
父親:
家族との絆や満足感が増し、自己効力感・幸福感が向上
仕事のモチベーションが上がる
夫婦:
信頼・尊重が育ちやすく、満足度の高い関係が長期的に続く
会話と笑いが増え、日常の小さな出来事に感謝し合える
男性の育児参加に関する国の取り組みとは?
日本では、政府や厚生労働省を中心に「父親の育児参加(男性の育児休業取得など)」を促進するための制度や施策がかなり整えられてきています。
ただし、制度の「形」だけではなく、「実態で使える・使われる」ための社会的・企業文化的な変化がまだ課題になっているという点にも注目しなくてはなりません。

まだわたしたちも知らない取り組みがたくさんあります。
長期で継続・普及され、少子化に役立つといいですね。
1. 産後パパ育休(出生時育児休業)制度
2022年10月から、改正育児・介護休業法により「産後パパ育休」が施行されました。
これは、子どもの出生後8週間以内に、父親が4週間まで育児休業を取得できる制度です。
この制度により、「赤ちゃんが生まれた直後に父親もサポートする時間」が法律で確保されるようになりました。
2. 育児・介護休業法の改正・制度の柔軟化
育児休業の分割取得が可能になるなど、育休を取得しやすくするための仕組みが強化されてきています。
具体的には、「1歳までの育休」を2回に分ける、など取得のタイミング・期間の選択肢を広げる改正が含まれます。
3. 企業への情報公開・公表義務
従業員数が一定以上の企業に対して、男性の育児休業取得率などのデータ公開を義務付ける制度があります。
透明性を高めることにより、企業間での責任や比較が促され、育休取得を後押しする社会的プレッシャー・インセンティブにつながるよう設計されています。
4. 目標設定政策
政府は、男性の育児休業取得率を高めるための数値目標を掲げています。
例えば、2025年までに男性育休取得率30%以上という目標。
また、「2030年までに85%の男性が育休を取得する」など、将来に向けた大きな目標も示されています。
5. プロジェクト・意識啓発の取り組み
意識調査と広報活動
若年層を対象に、育児休業取得意向や育児・仕事の両立に対する意識調査を実施し、その結果を公表することで、社会全体での意識を引き上げています。
また、若年層に響くクリエイター起用の動画・ショートドラマの制作など、広報の手段を多様化しています。
シンポジウム・企業との連携
政府・厚生労働省はシンポジウムを開催し、育休を取得している企業の事例を共有したり、取得しやすい制度の工夫・改善点を議論したりしています。
また、「イクボス宣言」や「イクメン企業宣言」をする企業を公に認めるなど、企業のリーダーシップを奨励する施策もあります。
課題とこれからの取り組み
制度が整ってきてはいるものの、「取得率は上がってきたが取得期間が短い」こと、また「取得したが職場の風土・周囲の理解が十分でない」ことが引き続き課題とされています。
また、以下のような取り組みが今後重視されていく見込みです。
夫に伝えたい”育て方のポイント”
「夫にも育児にもっと関わってほしい」と思いながら、どう伝えたらいいか悩む妻はとても多いです。
また、共働き家庭やワンオペ状態の家庭では、“夫が悪い”というよりも、“関わり方がわからない”男性が多いのが現実です。
ここでは、そんな家庭でも無理なく取り入れやすい「男性の育児参加の方法」を、妻が上手に伝えられる形で具体的にまとめました。

筆者が夫に育児を求める際に大事だと感じたのは、”やってほしいことを具体的に伝えること”。
男性の多くは、性質上「手伝った方がいいのはわかるけど、何をすべきかわからない」と感じているのです。
また、わたしは夫の「やってあげた感」にイラっとすることが多かったのですが、男性はしっかりと褒めたり感謝したりする方が、確実にやる気につながります。
夫を上手く育児に巻き込むためのポイントを、ぜひ参考にしてくださいね。
「完璧を求めず、”一緒に”を意識する」
夫に伝えたい最初のポイントは、「うまくやってほしい」より「一緒にやってほしい」というスタンスです。
多くの男性は、子どもの扱いに慣れていないため「ちゃんとできないから怖い」と感じています。
そのため、「やってみてくれるだけで助かる」「一緒にできると嬉しい」と伝える方が前向きに動きやすいです。
男性が今日からでもできる”簡単な行動”をお伝えしておきますね。
- 毎朝/毎晩「父の時間」を決める(例:寝る前の5〜10分の読み聞かせ)
- 1日1回は抱っこ・肌の触れ合いを意識する(特に乳児期のスキンシップ)
- お風呂・着替え・散歩など「父の担当」を一つ持つ(得意なことにすると◎)
- 遊びは“楽しく安全に挑戦”させる(家の中の冒険やボール遊びなど)
- 泣いたときはまず抱っこして落ち着かせる
- 会話を増やす((「どうしたい?」「何が一番楽しかった?」と子どもに問いかける習慣をつける)
- 週に1回は父子だけの外出(公園・買い物など)で“特別な思い出”を作る
また、夫に参加を促す際は、下記のような“共同作業の形”で頼むのがコツ。
- 「オムツ替え、慣れるまでは手伝ってもらえると嬉しいな」
- 「今日はお風呂に入れてくれると助かるな~」
- 「寝かしつけ、一緒にやってみよ!」
「タイミングを見てお願いする」
忙しい夫に「もっと関わって」と頭ごなしに言うと、責められたように感じて逆にやる気をなくす男性もいます。
効果的なのは、気持ちが落ち着いているときに具体的にお願いすることです。
例えば、「子どもをお風呂に入れてくれたら、その間にご飯の支度がスムーズにできるな~」というように、あなたが助かる理由をセットで伝えると、夫も「自分の行動が意味を持つ」と感じて動きやすくなります。
「小さな成功体験を積ませる」
男性は、“結果が見える関わり”を好みます。
そのため、最初から夜中の授乳のような大変なことを分担するよりも、成功しやすく感謝を伝えやすいことからスタートするのがコツ。
おすすめは、
- 子どもとのお風呂タイム
- 公園での遊び・散歩
- 絵本の読み聞かせ
- 寝かしつけ前のスキンシップ
これらは子どもも喜びやすく、夫自身も「楽しい」と感じやすいので、習慣につながりやすいです。
そして「パパがやると嬉しそうだね」「あなたがいると安心してる」と、感情ベースでフィードバックしてあげましょう。
「責めるより、感謝を言葉にする」
男性は“評価”に敏感な生き物。
妻の「ありがとう」や「助かった」という言葉が、育児参加のモチベーションを継続させる最大の力になります。
逆に、「やり方が違う」「遅い」「もっとこうして」などと責められると、自信を失って関わりが減る傾向に。
完璧さよりも関わる姿勢を褒める意識を持つと、夫は自発的に動くようになります。
「夫の得意分野を生かす」
元々家事や育児に抵抗がない男性を除き、夫にすべての育児を均等に分担するのは現実的ではありません。
そこで大切なのは、夫の性格・得意を活かした役割分担です。
- ロジカルな夫 → 子どものスケジュール管理や買い出し
- アクティブな夫 → 休日の外遊び担当
- 穏やかな夫 → 寝かしつけ・絵本係
- 機械に強い夫 → ベビーカー・家電などのメンテナンス
このように、無理なくできる分野から任せることで、自然に“頼られる心地よさ”を感じてもらえます。
「家庭を“チーム”にする」
最後に大切なのは、「パパに任せたい」ではなく「パパと一緒に育てたい」というメッセージを、日常の中で少しずつ伝えること。
「チームで育てている」という意識を共有できると、夫は「自分も家族の中心にいる」と感じ、責任感や愛着が生まれます。
その積み重ねが、自然で継続的な育児参加につながるのです。
まとめ
父親の育児参加は、単に「母親の負担を減らすため」ではなく、
- 子どもの発達を支える
- 母親の心を守る
- 家族の絆を強くする
という“三方よし”の行動です。
父親がほんの少しでも「共に感じ、共に動く」姿勢を持つだけで、家庭は確実に変わります。
多くの妻の本音は、「夫にもっとやってほしい」ではなく、「夫と一緒に感じてほしい」というもの。
行動よりも、気持ちの共有。家事よりも、心の理解。それができた瞬間に、妻は「この人となら、育児を頑張ろう」と思えるようになるんですよね。
共働きやワンオペ家庭での男性の育児参加は、”小さな成功体験”から始めるのがポイントです。
妻が“指導者”ではなく“パートナー”として感謝を伝えることで、夫は育児に自信と喜びを感じられるようになります。
そして、夫婦の関係そのものがより温かく、信頼に満ちたものに変わっていくのです。
一人でも多くの女性が、多方面での心理的メリットを感じられますように。

最後にもうひとつ。
父親が積極的に育児を行うと、母親と同じく「感情共感・育児応答」に関わる脳領域が活性化することが、研究で明らかになっています。
つまり、「育児脳」は性別ではなく経験によって育つのです。
ホルモン変化も同様です。
父親は赤ちゃんの泣き声や笑顔に触れることで、オキシトシンという愛情・絆ホルモンが上昇し、競争・支配性ホルモンであるテストステロンが低下する傾向があると報告されています。
男性も生物学的に「育児モード」に入れることが証明されているのです。
育児に自信がもてないパパに、ぜひ伝えてあげたいですね。
あとから読み返したいときに活用してくださいね。