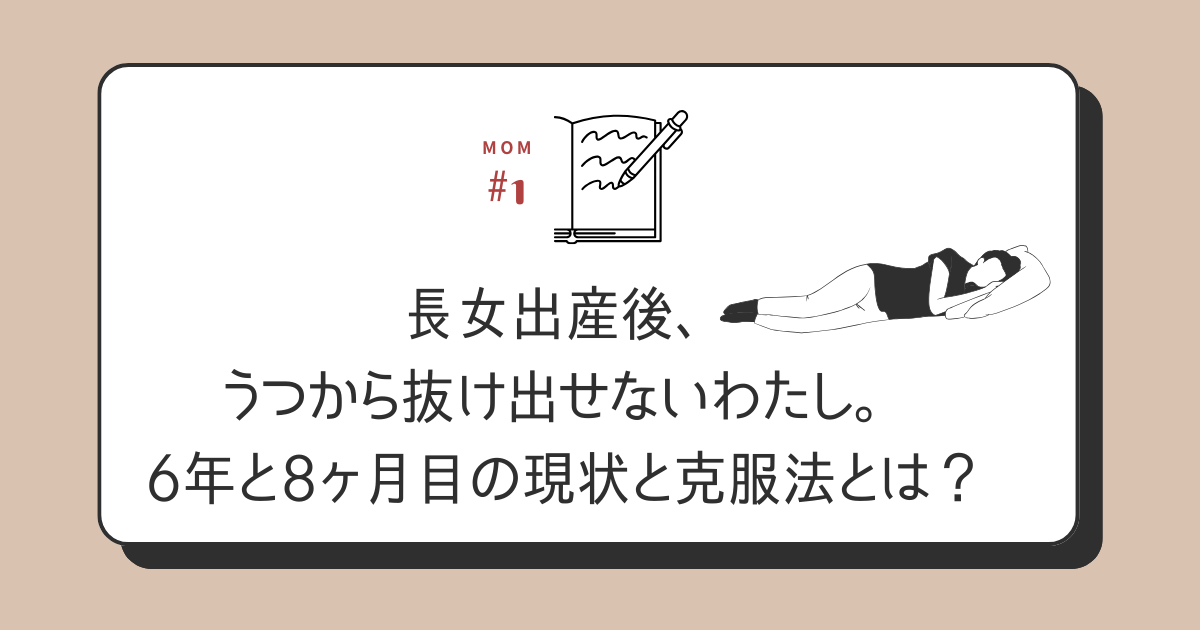
「今日もひどいこと言ってごめんね…」「最低な母親でごめんね…」
これは、すやすや眠る二人の娘たちの寝顔を見ながら毎晩のように筆者が思うことです。
イライラしたり、夫に怒ったり、子どもに当たったりし続けてきた6年間。
一緒に大きな声で笑い合ったり、子どもの前でいつもにこにこしている母親でいたいのに、そんな”ママとしての当たり前”ができないどころか、ヒステリックになってしまうこともありました。
これは恐らく、世間で”産後うつ”と呼ばれているもの。
このような状態が何年も続いた結果、自分に対する自己嫌悪が積み重なり、母親としての自分に「失格」「最低」「ありえない」などと批判してばかりでした。
でも実は、最近その”産後うつ状態”から「少し抜け出してきたかも」と感じ始めているんです。
産後うつは“心の病気”であると同時に、“環境が作り出すストレス障害”でもあります。
その環境が変わり始めた理由がいくつかあるので、この記事で詳しく紹介したいと思います。
- ”産後うつ”とは?
- 産後うつになってしまう理由
- 産後うつから抜け出すきっかけと克服法

わたしと同じように、「これって育児ノイローゼ?」と悩む女性や、「産後うつってどんな症状なの?」「いつまで続くの?」と不安を感じている方、筆者がどうやって克服の兆しを感じることができたのかを知りたい方は、ぜひ読んでみてくださいね。
そもそも”産後うつ”とは?
”産後うつ”は、出産後に起こる抑うつ状態のことで、医学的には”産後うつ病”と呼ばれるもの。
これは、出産を経験した女性の約10〜15%に見られる心の病気で、単なる育児疲れや一時的な気分の落ち込みとは全く違います。
産後うつは、いくつかの原因が同時に重なったときに起こりやすいのだそう。
また、産後うつによく見られる症状が2週間以上続く場合は、産後うつが疑われます。
長女出産後6年以上もの間続いた”状態”
まずは、筆者であるわたしがずっと抱えてきた状態についてお伝えしたいと思います。
今現在も「完全に克服できた」とは言い難く、これまでわたしが子どもたちに与え続けてきた”傷”を後悔するばかり。
また、情緒不安定な母親の姿や、辛そうな顔ばかり見て育つ娘たちに「この子たちはどんな大人になるんだろう」と恐怖心さえ抱きます。

楽しくポジティブに育児と向き合うことができているお母さんたちをよそ目に、わたしは”暗黒時代”とも呼ぶべき6年間を過ごしてきました。
望んで授かった待望の娘。本来なら幸せいっぱいな新生活のはずが、一体どんな日々を過ごしてきたのでしょうか。すべて正直にお話しします。
笑顔になれない・笑えない
これは、”産後うつ”の中で最も代表的な症状とも言われています。
頭では「笑いたい」と思っていても、体が反応しないのです。これは“怠け”や“気持ちの問題”ではなく、脳のエネルギー不足による機能低下なのだそう。
出産後、女性ホルモン(エストロゲン・プロゲステロン)の急激な低下や、睡眠不足・ストレスによって脳内の神経伝達物質(セロトニンやドーパミン)が減少します。
その結果、「嬉しい」「楽しい」という感情がわきにくくなり、表情の反応そのものが鈍くなるのです。
子どもたちがわたしに気をつかい、ふざけて笑わせようとしていることに気づいても、心から笑えず必死に笑顔を作っていました。
常に何かしらの不満がある
産後は「自分の思い通りにいかないこと」が増えます。
睡眠・食事・家事・夫婦関係・社会とのつながり——すべてが制限される中で、コントロール感を失うことが最大のストレス要因に。
そういうとき脳は”不安”や”不満”を通して、なんとか状況を整理しようとします。
つまり、常に何かに不満を感じてしまうのは、「このままでは崩れてしまう」という心のSOSサインでもあったのです。
また、夫に対して「わかってもらえない」「自分だけ我慢している」という思いが積み重なると、慢性的な怒りや虚しさに変わりやすくなります。
筆者の場合、授乳期間中の睡眠不足が一番つらく、それが”夫への不満”や”自己嫌悪”、そして”情緒不安定”といったすべての不調に繋がっていました。
ヒステリック・暴力的になる
感情を抑える理性(前頭前野)の働きは、ストレスや睡眠不足で弱まります。
その結果、脳の“怒りの中枢(扁桃体)”が過敏になり、怒りが瞬発的に爆発する結果に。
これは「性格が変わった」わけではなく、神経の抑制機能が限界に達している状態です。
怒った後に強い罪悪感を感じ、「こんな母親でごめん」と自分を責めてしまうことも多いですが、これは産後うつの典型的な悪循環。
例えば、夫が自分から協力してくれないときや、子どもが言うことを聞いてくれないときなどに、体の奥底から湧き上がる怒りが噴火するイメージです。
「こんな人間じゃなかったのに」と自分でも驚くほど、大声で怒鳴ったり泣きさけんだり、時には近くの物に当たったりしていました。
子どもの前で爆発を抑えられない
うつ状態では、理性的に感情を整理する余裕がなくなります。
そのため、子どもの泣き声やわがままが、「もうこれ以上耐えられない」というトリガーになりやすいのです。
特に、筆者のように「ワンオペ育児をしている」「実家が遠くて両親のサポートが受けられない」「夫が理解者でない」などといった場合、誰にも頼れず、全責任が自分にのしかかるため、感情の限界点が低くなります。
”怒りたくないのに止められない自分”を責めてしまう人が多いですが、これは“しつけの失敗”ではなく、脳の疲労と孤独の限界反応だったのです。
筆者の怒りやストレスの矛先は90%以上が”夫”。
理想とはかけ離れた”パパ”としての振る舞いにイライラや虚しさが積もり、頻繁に子どもの前で夫に怒り散らしたり、泣きながら訴えたりしていました。
子どもに対して支配的になる
産後うつでは、「コントロールを取り戻したい」という心理が強く働きます。
日常生活が思い通りにいかない中では、唯一自分が「支配できる」と感じられるのが”子ども”になりがち。
つい「こうしなきゃダメ」「言うことを聞きなさい」「やらないと〇〇だよ」といった強い口調や脅しのような行動に出てしまう背景には、「自分が崩れそうだから、せめて秩序を保ちたい」という無意識の防衛反応があります。
この状態が続くと、母親自身がさらに罪悪感を感じ、心の疲弊が深まるという悪循環に。
筆者は、良くないとわかっていながらも、「これ以上わたしに負担をかけないで」という気持ちが勝ってしまい、子どもたちの気持ちや行動を随分押さえつけてきてしまったと反省しています。
わたしが”産後うつ”になってしまった理由5つ
産後うつは、”心が弱いからなるもの”ではなく、いくつもの心理的・環境的・生理的要因が重なった結果だと言われています。

わたしが産後うつ状態に陥ってしまった5つの理由は、実はどれも産後うつを長引かせたり、悪化させたりしやすい代表的な要因だったのです。
睡眠不足
出産後、わたしが一番最初に直面した”睡眠不足”というストレス。
夜中の授乳や夜泣き対応が続くことで、深い眠り(ノンレム睡眠)を取れなくなる状態が続きました。
実はこれが産後うつの“入り口”であり、“回復を妨げる最大の敵”でもあったのです。
睡眠は、脳にとって「感情を整理する時間」。眠れない日々が続くと、感情のコントロールを司る前頭前野が疲弊し、怒り・不安・涙が制御できなくなります。
さらに、睡眠不足はセロトニンやドーパミンの分泌を減らし、“喜び”や“安らぎ”を感じる力そのものが落ちてしまいます。
わたしが「笑えない」「何をしても満たされない」という状態になってしまったのは、まさに脳が休息を失った結果だったのだと言えます。
”完璧主義”な性格
産後うつになったとはいえ、子どもに愛情を注がなくてはならない日々は続きます。
どんなに心身ともに疲弊していても子どもを喜ばせたくて、人形や知育玩具を手作りしたり、一緒に遊ぶ時間を優先したりと、さまざまな努力をしてきました。
でも、わたしの生活に”育児”が加わっても、家事が疎かになるのは許せなかったんです。
完璧主義なわたしは、「良い母でありたい」「家事も今まで通り完璧にやりたい」と自分に無意識のプレッシャーをかけていました。
出産後は環境が不安定で、理想通りにいかないことばかり。
「できていない自分」に焦点が向いてしまい、常に自分を責め続ける構図を知らず知らずのうちに作ってしまっていたのです。
このように、自責思考が積み重なると、心はどんどん疲弊します。
完璧主義は”愛の深さの裏返し”でもありますが、それゆえに自分への許しが足りなくなっていました。
非協力的な夫
「結婚しているのに孤独――。」
わたしが産後ずっと感じていたのは、育児や家事に非協力的な夫に対する心理的孤立感です。
「自分ばかり頑張っている」「理解されない」「助けてもらえない」という感覚は、心に「自分は一人だ」という絶望を植え付けます。
さらに、夫への期待が大きいほど、叶わないときの孤独感は強くなります。
産後すぐの頃、わたしに責められた夫が一度だけ「お前が母親なんだから当然だろ」といった発言をしたことがありました。
この出来事は、「わたしは本当に孤独なんだ」と思い込ませ、産後うつを悪化させる最大の心理要因のひとつとなってしまったのです。
本来、育児は”母親一人の仕事”ではなく、家族全体で支え合う営み。
夫の理解や共感が欠けていることで、“愛する力”よりも“耐える力”で日々を乗り切るようになっていました。
次女出産のタイミング
次女を出産するタイミングは、2歳を過ぎた長女の”イヤイヤ期”とちょうど重なりました。
出産後に十分な休養や心の回復ができないまま慌ただしい日々が始まったことで、身体的にも精神的にもリセットの余地がなく、新しい負担が積み重なっていったのです。
特に、ワンオペで上の子の育児をしながら妊娠・出産・授乳をする状況は、“完全な自己犠牲状態”。
このような状況では、脳が慢性的にストレスホルモン(コルチゾール)を出し続け、感情の安定が難しくなります。
「笑えない」「怒りっぽくなる」「涙が止まらない」などの症状が出やすくなるのは、自然な反応だったのです。
SNSなどで見る”理想”に感じる劣等感
SNSは、他人の“幸せの瞬間”だけが切り取られて流れる場所。
そんなことはずっと前からわかっていたはずなのに、産後の心は非常にデリケートで、「私もこうあるべき」「あの人はすごいのに自分は…」という比較の思考が強くなりやすい時期でした。
これまでは、「人は人、自分は自分」だと思ってサバサバと生きてきたつもりだったわたし。
でも、産後の孤独な時間の中でそれを何度も見ているうちに、「私はダメだ」「母親失格だ」という思い込みが深く刻まれてしまったのです。
例えば、同じ時期にママになった同年代の人が使っているベビーカーや赤ちゃん用のスキンケア、旦那さんがプレゼントしてくれた産後ケアなど、今となってはどうでもいいことばかり。
劣等感は、自分を奮い立たせる力にもなりますが、産後のようにエネルギーが枯れているときには自己否定の燃料になってしまいます。
心が疲れきっている時期ほど、「比べない」「見ない勇気」が必要だったのです。
産後うつから抜け出し始めたきっかけと克服法
「この産後うつ、いつまで続くんだろう…」
ネットで色々調べると目にする”半年”や”一年”という言葉は、わたしにとっては意味をなしていませんでした。
同じように産後のストレスを多く抱えているママ友たちとLINEで相談し合い、「わたしだけじゃない」と思えることをエネルギーに変えているような時期もありました。
でも、根本的な解決にはならないので、結局は「わたしだけの問題」と孤独を強めてしまうんですよね。
また、あるママ友は、「もう全部諦めたら、楽になった」と言っていたけれど、わたしにはなかなか諦めることができませんでした。
優しい性格の夫に対して、心のどこかで「いつか変わってくれるかもしれない」という期待を捨てきれなかったのです。

そんな不安定だった状況が、6年目にして克服の兆しを見せ始めた理由は、いくつかのきっかけが重なったからだと思っています。
誰にでも効果のある克服法とは言い切れないけれど、少しでも誰かの参考になれば嬉しいです。
義母と腹を割って話した
ストレスの絶頂期だった次女の産後。実は、遠く離れたところにいる義母に電話で不満をぶちまけたことがありました。
ところが、「わたしの苦悩を理解してもらいたい」とすがるような思いでとった行動だったのですが、これが裏目に。
「やっぱり義母が一番かわいいのは息子」だと痛感させられるだけに終わったのです。
それから約4年が経ち、久々に帰省した際に、義母とそのときの話題に。
すると、「あのときは厳しいことを言ったけど、悪いのは息子。あなたが苦しんだのは間違いなく息子のせいなのよ。」と義母が口にしたのです。
その瞬間、ずっとわたしの中にあったドロドロとした重いものがスーっと消えたような気がして、わたしもあのとき義母に不満を言ってしまったことを謝罪し、なんともスカッとする帰省になりました。
産後うつが長引いた原因には、”夫の母親”という感謝すべき偉大な存在に対する嫌悪感と、そんな気持ちを抱いてしまう嫌な自分への劣等感もあったんだと感じました。
夫を憐れむ気持ちが生まれた
普段は優しい夫。気分で態度が変わることがなく安定している人なので、不安定なわたしに逆上したり、文句を言ったりすることはなく、そんな夫に救われている部分はありました。
でも、気づかいや家事・育児となると、そのスキルはほぼ皆無。
これは、長女を出産して初めての子育てをするわたしにとってはかなり痛手だったのです。
それが最近になり、気にならなくなるどころか、「こんなこともできないなんて、かわいそう」と思うように。
これは、自分でも驚きの感情の芽生えでした。
例えば、脱いだ靴下をそのへんにほっぽり投げたままにするところや、使ったものを元の場所に戻せないところ。
これまではそんな些細なことに「イラっ」としたり文句が止まらなかったりしていたのに、今では感情の波風が立たないのです。
イライラしそうになったら、意図的に憐れむ気持ちを呼び起こすことで、子どもの前で夫に怒らなくて済んでいます。
”夫と対等でいること”をやめた
働き倒していた妊娠・出産前は、「夫とは対等でいたい」という強い思いがありました。
だからがっつり働いていたし、お金の管理や家事の分担なども、それなりに上手くできていたと思います。
そんなわたしのスタンスは、産後生活がガラッと変わっても変わることなく引き継がれていました。
「育児がこんなに大変なんだから、家事は半々にすべき」「お互い仕事してるのに、家事と育児の配分がおかしい」と。
しかし、その”思い込み”がストレスの一因になっていたのではと気付いたのです。
”今”を冷静に見つめ直すと、自分で稼いで自立していた以前とは違い、現在は仕事の忙しさはもとより、収入面も大半を夫に頼る生活。
「育児や家事を対等に求めるのは違うのでは?」と考えるようになったとたん、不満を感じることが一気に減りました。
「夫が疲れているであろうときは、無理にサポートを求めない。できることはわたしがやろう。」
というスタンスに切り替えてから、気持ちも楽になったのです。
”適当な自分”に対する抵抗感がなくなった
「離乳食はすべてオーガニックで」「肌に触れるものは無添加で」
産後はいろんなことに気をつかい、こだわっていました。
また、離乳後も「なるべく手作りのご飯を食べさせたい」と、コンビニやスーパーのお惣菜でさえ極力避けていたのです。
わたしが風邪でダウンした日にお惣菜を買ったときの罪悪感ときたら、何日も引きずるほどでした。
でも、仕事復帰後は、自分のことや子どもたちのあれこれに追われる中で、徐々に「それどころではない」という状況が増え、「お惣菜に頼りたい」と感じるように。
しかも、それを食べる子どもたちの嬉しそうな顔…♥
こうして少しずつ手を抜くことに対する抵抗感が薄れていき、今では疲れたときは堂々とサボることができるようになったのです。
今では、土日は一切キッチンに立たない週もあるほど。
子どもたちには、正直に「ママ今日はゆっくりしたいからUberにしよっかな!」と伝えます。
子どもと”本音”を話し合うことが増えた
どうしても”イライラ”を止められないわたしが子どもたちの心を少しでも救うべく実践し始めたのが、”本音を伝え合うこと”。
感情をありのままに伝え、怒ってしまった理由をわかりやすく説明するようにしたんです。
これは、娘たちがまだ3歳と1歳だった頃から寝る前に布団に入った状態で実践しています。
最初の頃は「?」だった娘たち。でも、ゆっくりと丁寧に伝えることで、何となく事情を理解し、わたしに対する警戒心を解いてくれているような気がしました。
6歳と4歳になった今では、イライラして当たってしまったわたしの説明や謝罪に対して、「ママ血の出る日(生理)だったんでしょ」「大丈夫だよ」「こっちも全然お片付けしなくてごめんね」と言ってくれたりもします。
「わたしが不機嫌なのはあななたちのせいじゃない」「あなたたちは悪くないんだよ」と知って欲しくて始めたことですが、気持ちを伝え合えるようになってから、後悔や罪悪感に苦しむことが減りました。
「夫より得してる」と考えるようになった
いつか育児がひと段落したとき。子どもたちが自立したとき。
わたしはきっと、「自分の子育ては十分じゃなかった」「もっと心を守ってあげたかった」と後悔するでしょう。
そして、「もっと一緒にいたかった」「あっという間に巣立ってしまった」と寂しさに苛まれることでしょう。
だから、心に言い聞かせたんです。
「夫よりも子どもたちと一緒に過ごす時間が長くて、たくさんの成長を目の当たりにできるわたしは幸せ者だ」と。
以前は、「わたしばっかり子どもの世話をしてる」「なんで代わってくれないの」という不満ばかり感じていました。
でも、こんなふうに思ったことは、10年後に後悔となってきっとわたしを苦しめる…。
「こんなにも手がかかる今が一番いい時期なんだ」と思って子どもたちに向き合うようになってから、イライラすることが減りました。
まとめ
子育てに苦悩を抱える女性の多くが、「このままで終わりたくない」「また笑って過ごしたい」と思えた瞬間を“光”として挙げています。
それは決して前向きな気分のときではなく、むしろ涙の中で静かに芽生える“希望”のようなもの。
こうした小さな意欲が戻ることこそ、回復の始まりです。
心の中で「また生きてみよう」と思えた瞬間、産後うつは確実に出口へ向かい始めるのです。
また、回復のきっかけとしてとても多いのが、「ちゃんとしなくても、なんとかなる」「家が散らかってても、生きてればいい」という小さな“あきらめ”や“許し”です。
これまで頑張りすぎていた女性ほど、「すべてをきちんとやらなきゃ」と自分を縛ってきました。
でもある日、体も心も動かなくなり、「もう無理」と思ったその瞬間に、逆に楽になったという声も多いです。
それは“諦め”ではなく、“力の抜けた愛し方”の始まり。
完璧を手放した瞬間、心に「人間らしい温かさ」が戻ってくるのです。

肩の力を抜き、「心が解放され始めた」と感じられるようになるまで、わたしは6年と8ヶ月もかかってしまいました。
わたしの場合、産後うつが長引いたのは、長年の間心の底に蓄積された”こうあるべき”という間違ったスタンスや期待、そして自分への罪悪感や心残りが原因だったのです。
でも今は、ようやく「なんだか今のわたし、最強かも」と感じられるときもあるほど。
子どもにとっては、”家事を完ぺきにこなすママ”よりも、”いつも笑顔のママ”。
そんな”当たり前”なスタートラインに、6年目でようやく立つことができたように思います。
筆者がこのまま産後うつを完全に乗り越えられるか、この先もどうかあたたかく見守っていてくださいね♥
あとから読み返したいときに活用してくださいね。

