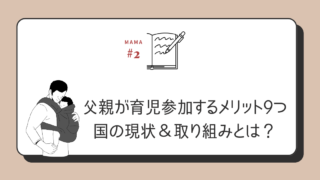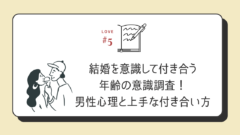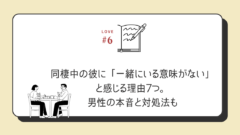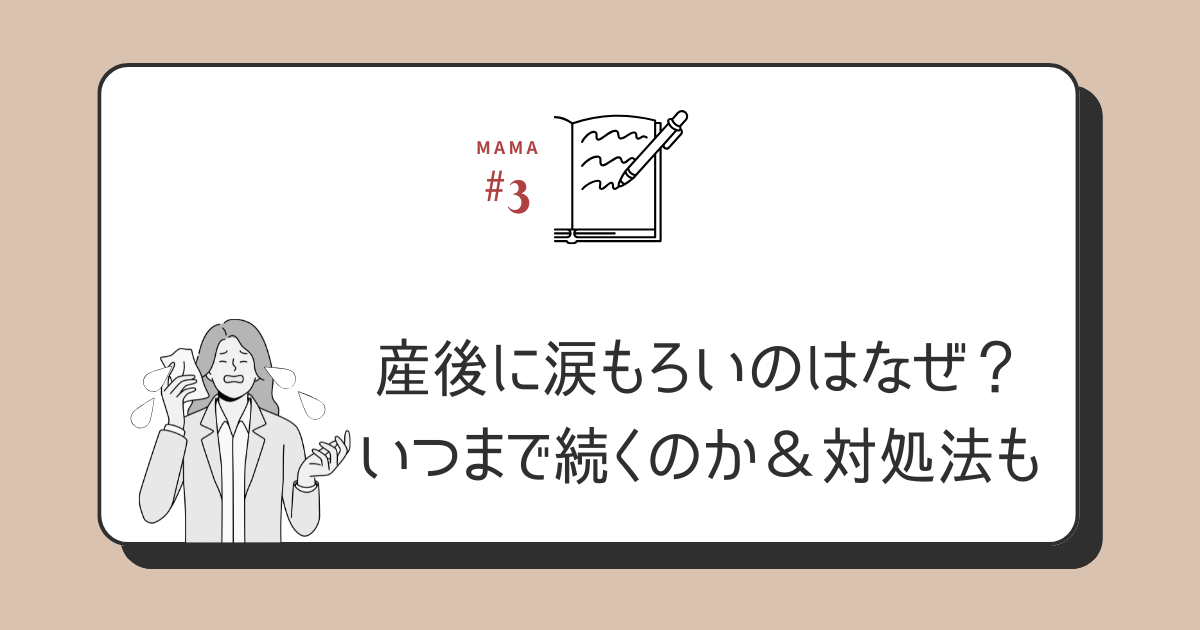
産後の女性には、心と身体にさまざまな変化が生じるもの。
そのほとんどが女性にとってストレスになるようなネガティブな変化で、長期にわたり苦しむ人もいるほどです。
その中で意外と多いのが、”産後の涙もろい自分”に対する戸惑い。
実は、産後の涙もろさは、妊娠・出産に伴う急激なホルモンバランスの変化が原因で起こるマタニティブルーであることが多く、通常は1~2週間ほどで自然に回復します。
しかし、症状が2週間~3ヶ月以上続き、抑うつ気分や不眠、食欲不振などの他の症状を伴う場合は、初期の産後うつの可能性も考えられるため、早めに専門機関に相談することが大切です。
- 産後の女性が”涙もろい状態”になる理由
- ”涙もろい状態”は産後いつまで続くの?
- ”涙もろい状態”から抜け出すための対処法

筆者であるわたしは元々涙もろい性格だったのですが、産後はさらに涙もろく。
映画の予告CMのようなたった10秒ほどの動画に号泣させられるほどで、まさに涙腺崩壊状態でした。
産後うつやホルモンバランスの変化によって精神不安定になりやすい時期とはいえ、「自分じゃない」と感じるほどの気持ちの変化に恐怖心さえ抱いたほど。
この記事ではその原因を詳しく掘り下げるとともに、対処法もお伝えしますね。
多くの女性が産後に「涙もろい」と感じる場面

産後に女性が「異常に涙もろい」「私ってこんなに涙もろかったっけ?」などと感じるのは、単に悲しいという理由だけではありません。
その涙には、喜び・不安・孤独・疲労・安心など、さまざまな感情が入り混じっているため、「情緒不安定になった」と感じる人が多いんです。
まずは、実際によく見られる具体的な場面を挙げてみましょう。
赤ちゃんを見つめているとき
産後の女性は、生まれたばかりの我が子を見て、
と喜びと感動が一気にあふれ、涙が出ることがあります。
特に、出産の痛みや入院中の不安を乗り越えた直後は、ホルモン(オキシトシン)の影響もあり、退院して気持ちがひと段落すると涙が止まらない人も多いです。
しかし一方で、我が子の寝顔を見ながら「こんな母親でごめんね…」「この先どうなるんだろう」という不安の涙を流す人も。
授乳中・夜中の赤ちゃんの泣き声を聞いたとき
こうした状況が続くと、「私が悪いのかな」「もう無理かも」と無力感や自己否定感から涙がこぼれることがあります。
特に、夜中に暗い部屋の中で一人で赤ちゃんをあやしている時に泣いてしまう人はとても多いです。
また、寝不足が続けば続くほど精神不安定になり、赤ちゃんの泣き声を聞くたびに心臓がビクビクしてしまう人も。
そんな自分に対する自己嫌悪感で涙が出るケースもあります。
周囲の言葉や態度が気になったとき
産後は、夫や親からの何気ない一言が必要以上に耳に残ったり、心が傷ついたりすることが多くなりがち。
といった言葉に傷ついたり悲しくなったりして涙が出やすくなります。

筆者も周囲の何気ない言葉に敏感な時期がありました。
次女を出産したときにイヤイヤ期真っ最中だった長女。目覚めと同時に服をすべて脱ぎ捨て、よく全裸で逃げ回っていました。
そんな時に受けた、義母からの「女の子なんだから、服ぐらい着せてあげて」という一言。
悪気がないのはわかっていても、当時のその一言はわたしにとって”地雷”でしかありませんでした。
一方で、夫が優しく「ありがとう」「頑張ってるね」と言ってくれた瞬間に安心して泣く女性もいます。
社会との距離を感じたとき
こうした瞬間に孤独感や取り残されたような気持ちから涙が出ることがあります。
これは、「出産前の自分」と「今の自分」のギャップに、誰もが初めて戸惑う場面のひとつ。

筆者は慌ただしく過ぎていく日々の中で、ふと鏡をみた瞬間に外の世界との距離を感じて涙が出たことがあります。
寝不足でお風呂に入る気力も時間もなく2~3日おきだった時期に、我に返った自分が頭ボサボサ、目の下真っ黒という状態があまりにも惨めで、言葉を失ったことも。
病院や検診で不安を感じたとき
退院時の赤ちゃんの体重が出生時よりも下回るのはよくあること。
これは、特に産後~入院中、そして1ヶ月健診までの女性にとって、涙が止まらない大きな原因になりやすいです。
このように、思い通りにいかない毎日に、「ちゃんと育てられてないかも」「母親失格かも」と不安になり涙ぐむことがあります。
健診で子どもの状態について小さな指摘を受けた場合も、大きな問題でなくても次の健診までの期間にあれこれと検索することに必死になったり、不安に駆られたりして過ごすことになります。
また、医師や助産師の励ましなどを受けたときに、自分の情けなさが恥ずかしくなったり、弱気で頼りない自分に嫌悪感を感じて泣いてしまうケースも。
家族や周囲の支えを感じたとき
そんな小さな優しさに感謝と安堵の涙を流す女性もいます。これは、それまで張りつめていた心がほぐれる瞬間。
また、地域の保健師さんやママ友に「分かるよ」「十分頑張ってるよ」などと言われたとき、孤独の中で共感してもらえたことに安心の涙を流す人も多いです。
「やっと分かってもらえた」「自分だけじゃなかった」と感じると、ずっと緊張状態だった心が緩むのです。
自分の時間をもてた瞬間
そんな“ほんの数分”に涙が出ることもあります。
産後は、自分の体力も時間もすべて赤ちゃんに向けることになり、出産前のような時間の余裕は一切なくなるもの。
「こんなことで泣くなんて変かも」と思うかもしれませんが、その涙はそれだけ心が頑張っていた証拠です。
赤ちゃんの成長を感じたとき
こうした瞬間には、感動と産後の苦労が報われた思いが重なり、自然と涙もろい自分になりやすいです。

筆者はふと産後の写真を見返したときに「こんなに小さかったのに…」という成長への感謝の涙を流すことがよくありました。
それだけでなく、「どんどん成長していく娘に対してわたしはまだまだ子ども」「こんな泣き虫な母親じゃダメた」と感じることも多かったです。
理由もないのに泣きたくなるとき
特に明確な理由がなくても、突然涙が出ることがあります。
例えば、ボーっとテレビを見ているときや、家事をしているときに泣いてしまうケースが多いです。
これは、ホルモンバランスの変化と睡眠不足・ストレスが重なった結果、感情のバランスを取るために涙が出る自然な現象です。
しかし、「理由もないのに泣くなんて”産後うつ”かもしれない…」と思い悩み、育児に対する自信がもてなくなるという悪循環に陥ってしまう女性もいます。
産後の女性が涙もろい状態になる原因
多くの女性が産後に「涙もろい」と感じるのは、ホルモンの変化・心の疲労・新しい役割への戸惑いなど、いくつもの原因が関係しています。

ほとんどの場合、産後の涙もろさは「心が弱くなった」のではなく、ホルモンバランスの自然な変動によって感情が敏感になっている状態です。
これは、多くの女性が経験する産後の一時的な心の揺れであり、時間の経過とともに徐々に落ち着いていくのが一般的。
しかし、すでに心の限界が近く、受診やサポートが必要な”黄色信号”の可能性も0ではありません。
正しい対処法を知るために、原因をしっかりと見極めていきましょう。
ホルモンの急激な変化
出産直後は胎盤が体外に出ることで、妊娠中に高かったエストロゲンやプロゲステロンが急激に減少します。これが脳内の神経伝達物質(セロトニンやドーパミン)のバランスを乱し、情緒不安定になりやすくなります。
加えて、プロラクチン(授乳を促すホルモン)やオキシトシン(愛着を深めるホルモン)の変動も感情に影響します。
これらのホルモンは”涙もろさ”や”感受性・敏感さ”を促進する働きがあります。
これらのホルモンは、心の安定や感情のコントロールに深く関わっているため、急に減ることで涙もろくなることの他にも次のような影響が出やすくなります。
睡眠不足と慢性的な疲労
睡眠不足と慢性的な疲労も、産後の女性が涙もろくなる大きな原因のひとつ。
夜間の授乳や24時間絶え間なく続く赤ちゃんのお世話で慢性的に睡眠が分断されると、感情制御能力が低下します。
脳が疲れていると、些細な刺激で感情があふれやすくなり、涙が出やすい状態に。
また、育児では身体的な疲労も蓄積します。授乳・抱っこ・寝かしつけ・家事などで一日中体を酷使することで、
筋肉の疲れや肩こり・頭痛・倦怠感などが続き、心にも次のような影響を及ぼします。
このように、心と体の疲労が連動して感情が抑えにくくなることが、涙もろさを引き起こす大きな原因なのです。
精神的プレッシャー・責任感
多くの女性が、「ちゃんと育てなきゃ」「泣かせたらかわいそう」「母親なんだから頑張らなきゃ」と自分に厳しくなりがちです。
しかし、育児は想像以上に思い通りにいかないもの。理想と現実のギャップに直面すると、無力感や自己否定を感じ、涙が出てしまいます。
中には、赤ちゃんが泣くたびに「何かしてあげないと」「私のせいかも」と思ってしまい、自分を責める女性も。
この“常に気を張った状態”が続くことで、心が疲弊して涙が出やすくなるのです。

筆者の場合、夫が育児や家事に積極的でなく、実家も遠かったため、「全部ひとりでやらなければ」というプレッシャーを背負っていました。
また、次女出産後、長女に手を焼いている間は次女を泣かせっぱなし。「抱っこしてあげたいけど長女のメンタルも守らなきゃいけない」というプレッシャーは本当につらいものでした。
アイデンティティの喪失感・孤独感
出産を経て、女性は”母親”という新しい役割を担います。
それ自体は素晴らしい変化ですが、次のような状態が涙もろさや情緒不安定さを引き起こします。
つまり、“女性としての自分”から“母親としての自分”への急激な変化により、これまでの自分が消えてしまったような喪失感や孤独感を覚えるのです。
ほっとしたときの反動
出産や育児は、想像以上に緊張とストレスの連続。
心も体もずっと「頑張らなきゃ」「気を張らなきゃ」という状態が続いているため、ふとした瞬間にその緊張の糸が切れたように涙があふれやすくなります。
産後しばらく経ってもホっとした瞬間に涙が出るのは、「もう少し頑張れそう」「私はひとりじゃない」と感じた瞬間に、心が緊張から解放されるから。
特に、夫へのストレスや不満、発育の不安などが解消された瞬間に、涙という形で感情があふれ出しやすくなります。
過去のトラウマの表面化
出産という大きなライフイベントは、心身に強い刺激を与えるだけでなく、無意識に”過去の記憶”や”心の傷”を呼び起こすきっかけになってしまうこともあります。
出産は命を生み出す行為でありながら、痛み・恐怖・命の危険などを伴う”生死の体験”。
この体験が、心の深い部分に眠っていた過去の不安・喪失・恐怖の記憶を刺激すると、
といった過去のネガティブな体験を思い出してしまいが再び、涙となって現れることがあります。
出産後に母親という立場になったことで、「母に愛されていなかったのでは」と感じた記憶や「母のようにはなりたくない」という思いを思い出したり、重ねて考えたりする女性も少なくありません。
身体的問題
出産後は、一部の女性に”産後甲状腺炎”が起こることがあります。
これは免疫バランスの乱れにより、甲状腺ホルモンが過剰または不足する状態。このホルモンは体の代謝だけでなく、気分・集中力・感情安定にも影響を与えます。
以下のような症状を「気持ちの問題」と思い込んで放置すると悪化する場合もあります。
また、出産や授乳で大量の栄養が消費されるため、鉄欠乏性貧血やビタミンB群の不足も起こりやすくなります。
これらが不足すると、抑うつ・不安・涙もろさといった精神的症状が現れます。
マタニティブルーズ・産後うつ
産後の女性が涙もろくなる原因のひとつに、マタニティブルーズや産後うつが関係しているケースがあります。
マタニティブルーズは、出産後2〜10日頃に多く見られる一時的な情緒不安定の状態で、原因は主にホルモンバランスの急激な変化や、出産による体力消耗・環境の変化です。
この時期の女性は涙もろくなり、理由が分からないまま泣いてしまう、気分が沈む、集中力が続かないなどの症状が出ますが、ほとんどの場合は1〜2週間ほどで自然に回復します。
一方で、産後うつはより長期的かつ重度の精神的落ち込みが特徴。
産後2週間を過ぎても強い不安や悲しみ、涙もろさが続く場合は、初期の産後うつが疑われます。
原因にはホルモンの変動だけでなく、育児ストレス・孤立感・パートナーのサポート不足などが複合的に関係しています。
つまり、産後の涙もろさが「一時的な情緒変化」か「うつ症状の始まり」かを見極めることが大切なのです。
産後の”涙もろい状態”はいつまで続く?
産後の“涙もろい状態”がいつまで続くのかは、個人差が大きいもの。
多くの女性は、
- 2週間〜1か月で軽快
- 3か月以内に安定
していくケースが一般的ですが、体力やサポート環境、性格(完璧主義・我慢強いタイプなど)によっては半年〜1年以上かけて回復する人もいます。
ただし、「時間がかかる=弱い」ではなく、その人のペースで着実に心は回復していきます。

筆者が経験したのは、まさに”産後うつ”。6年経った今でもまだ完全に回復したとは言えません。
ただ、6年はかなり長い方だと。ここまで長引いてしまったのは、地域のサポートや受診を避けてきたことも一因かもしれません。
また、自身の性格や夫のサポートの有無もとても大きいと実感しています。
① 一時的なマタニティブルーズ:およそ2週間以内
出産後3〜5日ごろから涙もろくなる場合は、ホルモンの急激な変化による自然な反応です。
多くの場合は1〜2週間ほどで自然に落ち着くことが多いです。
この時期は「心が不安定な状態が普通」なので、無理に元気になろうとする必要はありません。
② 睡眠不足・育児ストレス:3か月を目安に徐々に回復
出産の疲れ・寝不足・生活リズムの乱れなどが続くと、涙もろさも長引くことがあります。
産後3ヶ月という時期は、以下のような特徴があります。
この時期に涙もろさが残っていても自然な範囲ですが、「徐々に悪化している」と感じる場合は要注意。
心のプレッシャーや疲れが蓄積しているため、何の対処もせずに放置すると産後うつに移行してしまう可能性が高くなります。
③ 精神的負担・産後うつの可能性:3か月以上
3か月を過ぎても涙もろさや気分の落ち込みが強い場合は、単なるホルモン変化だけでなく、心理的・環境的ストレスの影響が大きい可能性大。
特に、以下のような症状がある場合は注意が必要です。
これらがある場合は、心療内科・精神科・産婦人科・地域の保健師などに早めに相談することが大切です。
早期に支援を受けることで、ほとんどの人がしっかり回復できます。
産後の涙もろさを和らげるための対処法
「涙もろさ」は、産後多くの女性が経験する自然な反応。
ネガティブな涙ばかりではなく幸せな瞬間もあるためつい見逃してしまいがちですが、放っておくと心身の疲労が積み重なり、産後うつに発展することもあります。
ここでは、そうならないために、”心・体・環境”の3つの視点から、効果的な対処法を詳しく解説します。

筆者の場合、産後の涙もろさの原因が”産後うつ”だという自覚がありました。
しかし、助けを求められない・求めたくない自分の頑固さと完璧主義な性格が、その状況を長引かせてしまっていたんです。
早めに対処すれば、わたしのように長期間苦しみ続けるのを防げるとともに、「育児って楽しい」「子どもってかわいい」と子育てに喜びや幸せを感じることができるようになりますよ。
心のケア
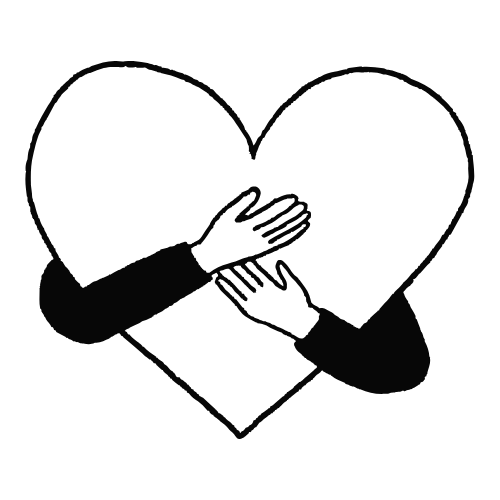
「泣いてもいい」と自分を許す
涙を流すのは、心の廃棄物を排出するために大切なこと。無理に我慢するとストレスが溜まります。
そこで、「泣く=弱い」ではなく、「泣ける=心が生きている証拠」と考えるようにしましょう。
涙を流した後は、脳内のオキシトシンやセロトニンが分泌されて心が落ち着きやすくなります。
感情を言葉にする
自分の中で「しんどい」「寂しい」と思っていても、言葉にしないと整理はできません。
一番は信頼できるママ友や両親に話すことですが、心がふさぎ込んでいるときには「話したくない」と感じてしまいがち。
そんな場合は、SNSやママコミュニティに投稿したり、日記やスマホメモに書くことで、ストレスや不満が外に吐き出されて心が軽くなります。
完璧を目指さない
「ちゃんとやらなきゃ」「母親だから頑張らないと」と思うほど涙が増えます。
“できていない自分”を責めるのではなく、「今日も慣れない育児、よくやった!」と自分を認めましょう。
赤ちゃんが無事に1日を過ごしただけで十分立派です。
身体のケア
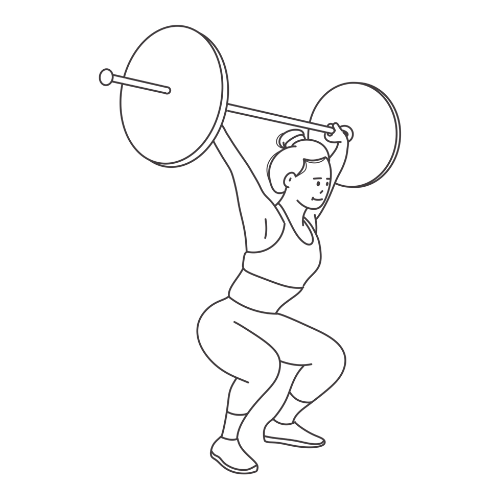
睡眠を最優先にする
産後の涙もろさの最大の要因は睡眠不足です。
家事が滞っていたとしても、今は15分でも昼寝する「休む勇気」が心を守ります。
赤ちゃんが寝たら家事よりまず休むこと。そして、時には夫や家族に夜間のミルクやおむつ替えを頼むことも必要です。
栄養を意識する
ホルモンバランスを整えるには、鉄分・ビタミンB群・たんぱく質が重要です。
ホルモンバランスを味方につければ、自然とイライラや悲しい気持ちも減っていきますよ。
外の空気を吸う
太陽光を浴びるとセロトニンが分泌され、気分が上がります。
玄関の外など出られるところならどこでもいいので、5分外に出ることを心がけてみましょう。
イライラしたら、その場から立ち去りベランダに出るだけでも効果があります。
環境のケア

「手伝って」ではなく頼み方を工夫する
夫や家族にサポートを求める際は、「何をどうしてほしいか」を具体的に伝えましょう。
例えば、「洗濯を畳むのをお願いしたい」「30分だけ赤ちゃんを見ててほしい」など。
特に男性は性質上、“具体的なお願い”の方が動きやすく、結果的にあなたの負担が減ります。
サポート制度を活用する
日本では各自治体に以下のような支援があります。
「助けて」と言うのは勇気のいることですが、それは母としての責任ある行動ですよ。
同じ経験をした人と話す
ママ友やママ同士のグループLINEなどで、「私も泣いてた」と聞くだけで心が救われるもの。
共感はあなたの孤独感を和らげ、心を守る力になります。
あえて言わないだけで、周囲のママたちのほとんどが同じようにつらさを感じていますよ。
涙が止まらない時の即効セルフケア
まとめ
産後の涙もろさは、
が重なって起こる、どんな女性にも起こりうる自然な反応です。
大切なポイントは、泣くことを悪いことと捉えず、「あなたの心が頑張っているサイン」として受け止めること。
そして、頼る・休む・話す——この3つを意識することが、最も効果的な対処法です。
また、涙もろいのは心の弱さではなく、身体の回復がまだ整っていないサインであることが多いです。
感情の乱高下が続いたり、涙が止まらない、無気力感が強い場合や、それが3ヶ月以上続く場合は、産婦人科や内科で血液検査を受けるなどして身体的な原因を確認することも必要です。

産後に子ども向けアニメや映画を観ると、登場人物を自分の子どもに置き換えてしまい、感動しやすくなったと感じませんか?
これは、子どもに対するあなたの愛情の深さの証でもあります。
一生懸命な日々を送っているからこそ、つい息抜きを後回しにしてしまうんですよね。
これからは、適度に手を抜くこと、そして頼れるものには頼ること。
筆者もまだまだ修行の身です。一緒に少しずつ笑顔を増やしていきましょうね。
あとから読み返したいときに活用してくださいね。